![]()
・5月4日(水)古本探求 校友会雑誌の思い出 講師 鈴木春雄

・6月12日(土) 私のフランス 講師 作家 加賀乙彦氏
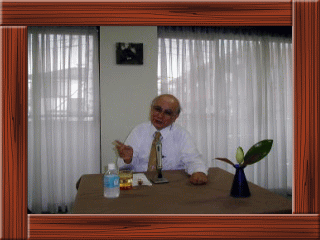
1957年のパリ留学でのフランスの話。船で40日かけてパリに行かれたそうで、
船で一緒だった方は、留学後もいろいろな方面で活躍された人たちでした。
天才フルーティストと言われた故加藤恕彦氏と一緒だったと言う事は、驚きました。
次にフランスの留学のお話。フランスの医師達は長い食事とワインをとるため帰宅して午後はいなかっ たそうです。その中医者である加賀氏が病棟に午後来ると看護婦さんは怒るそうです。加賀氏は看護婦 さんに頼んで、会話の練習の為にお話をしたいという場を作り、
患者の方とお話をされたこと。患者さんの言葉を書き取ったり、スペルを患者さんから教えてもらい
フランス語会話が出来るようになった。(患者さんから話を聞くというのは、カウンセルしていることですよね。 直接加賀氏は病状が良くなったと言われてませんが、その患者さんとのやりとりを聞いているとこれは 病状が良い方に向いていったのではと素人でありながらそう判断してしまいました)。
また、教会の建築について言及され建築様式と美術の話からいかにキリスト教の存在が大きいか、最後 はオラショのお話を伺い感動してしまいました。とにかく1500年ヨーロッパの世界と交流がなかったことを様 々な例を出されてお話を伺いました。そして初めての休み岩田栄吉氏とオランダにいきフェルメールの「ミ ルクを注ぐ女」の秘密も聞いてしまいました。
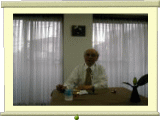
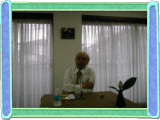
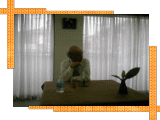

お話が終わり、コーヒーやおいしいケーキをいただきながらなお、話が続きました。
映画「THE PASSION OF THE CHRIST」のキリストの受難のシーンの話に及びました。キリストは
ひどい目に遭いますがあの苦労よりは、まだましだと思い、ジャンヌ・ダルクやマリア・テレサは
自分の苦しみを耐える事が出来たと話されました。私は、キックボクシングを趣味でやっていますが、
キックを受け手も大丈夫なように竹刀で両太ももをたくさんたたかれたことがあります。(けっこうたくさんです) あの痛さは、なかなかつらいものでパッションを見たらあのキリストの痛さがとてつもないものだと
実感しました。

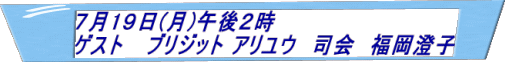
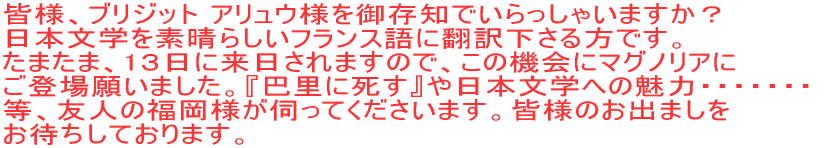
![]()
![]()
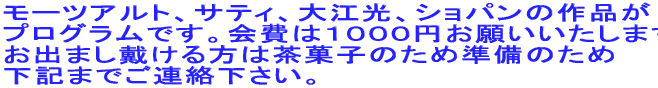
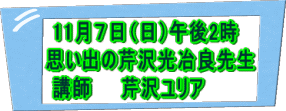
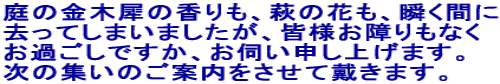
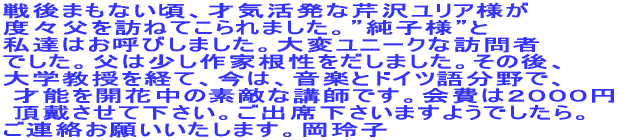
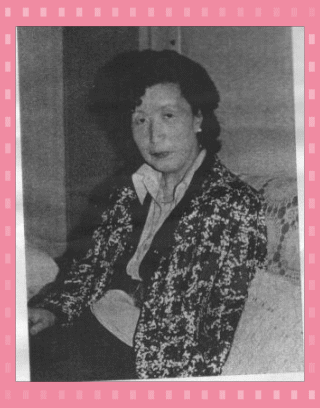
芹沢ユリア氏は、才気煥発で英語、フランス語、ドイツ語、日本語を治めた方で
さらにヴァイオリンも本格的に学び、この日のお話は、芹沢光治良の「巴里に死す」「巴里婦人」を
読み、「巴里婦人」に夢中になったこと。カトリックの事。ウイーンフイルハーモニー、
森有礼氏や渡仏した時の船の様子など様々な話に及びました。
![]()
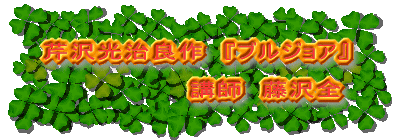
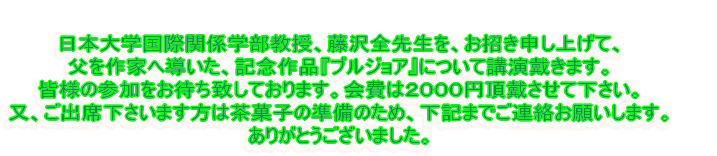
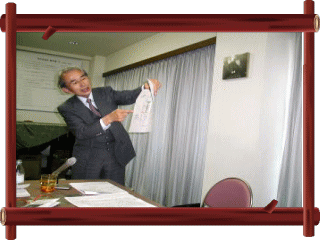
先生は、井上靖の研究家です。先生の講義は沢山の資料を使い
新しい読む視点に気がつかせてくれました。
ところで、先生は講演会の始まりで、芹沢文学を評価するのが
なかなか難しいと話されました。芹沢光治良研究は学会では残念ながら
停滞している。
日本近代文学学会では、芹沢光治良に強い眼差しが向けられていない。
同時に芹沢の場合は非常に手強い世界です。これがどういう場合か
と言うことで話が始まりました。
「ブルジョア」は、日本的な文学とは、全く違った形で書かれており、
これが日本にはなかなか受け入れられないし、日本語が良く読めれば
すぐ理解出来るということではない。
それはどういう事かという事を詳しく
お話しされました。 (文責 管理人)